|

|
【脳卒中の最新治療】 
|
脳卒中は疾病別死因の第3位であり、癌や心臓病と共に3大生活習慣病として関心が持たれています。また、脳卒中は片麻痺や言語障害などの後遺症を残すことが多く、「寝たきり」や介護が必要となる最大の原因になっています。
脳卒中は大きく分けると、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、脳内の血管が破裂する「脳出血」、脳血管にできた動脈瘤などが破裂する「クモ膜下出血」の3つのタイプがあります。最近では「脳梗塞」の割合が増えており、60〜70%を占めるようになってきています。
脳卒中診療は、MRIや超音波検査などの画像機器・診断の進歩、遺伝子組換え組織型プラスミノーゲン・アクチベータ(rt-PA)(血管に詰まった血栓(血のかたまり)を溶かす血栓溶解薬)などの新しい治療薬の開発、脳血管内治療の進歩などにより、この10年で大きな前進を遂げました。
特にrt-PA治療は脳卒中治療のあり方を大きく変えようとしています。わが国では、平成17年10月に発症3時間以内の脳梗塞に対してrt-PA静脈内投与が行えるようになりました。rt-PAは劇的な効果を示し、治療後早期より脳梗塞症状の改善が期待できます。ただし、頭蓋内出血をきたすこともあるため経験を積んだ専門医師が適切な設備を有する施設で、適応基準を十分に遵守して治療を行う必要があります。
近年、脳卒中は『ブレインアタック』として、どちらかというと消極的な治療対象であったものを、心筋梗塞の『ハートアタック』にならい積極的に治療を行うべき緊急疾患であるとして、脳卒中専門病棟の設置や主に神経内科医、脳神経外科医を中心とした専門チームによる診療体制の整備が進められています。
脳卒中は今や治せる病気になってきています。命の危険を防ぎ、後遺症を軽くするためには、できるだけ早い治療が重要です。もし、ご自身やご家族、周りの人に脳卒中の症状がみられたら、一刻も早く専門医を受診してください。
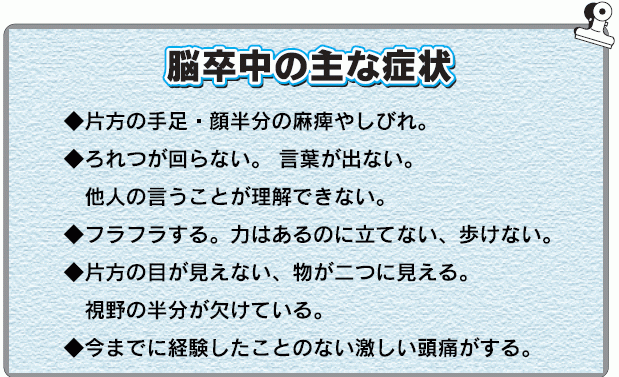
(文責 神経内科 荒川竜樹)
|

