|
もくじ |
| 第1号 H 12.4/1 |
| 病院広報誌発行にあたり |
| 内科第一紹介 |
| 看護部紹介 |
| 放射線部紹介 |
| 糖尿病教室案内 |
| 外来のご案内 |
| かけはしホーム |
|
外科第2は昭和56年10月の附属病院開設と同時に診療を開始し、現在に至っています。開設時は、主として心臓血管外科、呼吸器外科、消化管外科の3領域の診療を行っていましたが、平成7年には心臓血管外科が診療科として独立しました。現在の内田雄三教授は、昭和63年12月に調亟治前教授の後任として教授に昇任し、すでに12年目を迎えました。 教室員(4月1日現在)は内田教授以下、助教授1名、講師1名、助手6名、医員研修医7名、大学院生3名の総勢18名で診療に当たっています。年間の手術件数は、年によって多少の変動はあるものの、全身麻酔手術で約 350例前後です。当科が専門としている疾患は、食道・胃・大腸などの消化管の外科、呼吸器外科、その他の一般外科です。ほとんどの患者さんが主に県内の開業医の先生から紹介されておりますが、直接外来に来られる方もあります。
研究もさかんであり、(1)肺癌・負道癌の遺伝子・染色体の研究、(2)消化管の逆流症と発癌の因果関係に関する実験的検討、(3)消化管再建術の改良と機能評価、(4)食道運動機能障害に関する臨床的検討、(5)小腸大量切除後の小腸移植に関する基礎的研究など、忙しい臨床の合間をぬって精力的に行っています。 なお、大学在籍の医師は十数名ですが、医局員の総勢はlOO名を越え、県内外の約30施設で診療ならびに研究に従事しております。そして、各病院の仕事を終えた夜には多くの若手医局員が教室に集まり、研究室の明かりは深夜まで消えることがありません。 最後に、内田教授は現在、日本胸部外科学会会長の要職をつとめており、本年10月には、これまでの教室の成果の集大成ともいうべき第53回日本胸部外科学会総会を別府の地で開催いたします。学会最終日翌日には『日本人と臓器移植』というテーマで市民公開講座(大分県総合文化センター・グランシアタ、10月28日 (土))を開催しますので、多数の皆様方のご来場をお持ちしております。 (文責 野口 剛) |


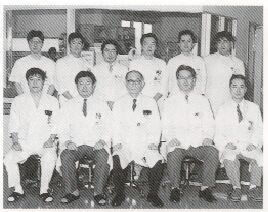 呼吸器グループでは、気管支・肺および縦隔の良性および悪性腫瘍を中心に年間約150例の手術があり、このうち胸腔鏡下手術が30%を越えています。これは従来のごとく胸を大きく切開せず、3〜4個所の小さい穴をあけて内視鏡と手術器具を挿入し手術を行う方法で、患者さんの負担は明らかに減少し、手術後の回復も早く、適応となる患者さんには積極的に行っています。消化器一般外科グループでは年間約200例の手術を行っており、特に食道癌の患者数は県内では一番多く、九州内でもトップクラスの実績です。その手術成績も、lCU(集中治療部)の専門医による卓越した手術後の集中管理のおかげもあって極めて良好であり、全国的に高い評価を受けています。内田教授がライフワークとしてきた食道手術のこの20年間の経験をもとに、今後さらに合理的な手術、すなわち患者さんごとに手術範囲(特にリンパ節の切除範囲)を考慮したり、先に述べたような内視鏡下手術なども取り入れていきたいと考えています。また、胃の手術後の小腸を用いた代用胃を使った胃再建術においても、様々な工夫を行い、手術後の症状を軽減することに成功しており、国内外の評価を受けています。
呼吸器グループでは、気管支・肺および縦隔の良性および悪性腫瘍を中心に年間約150例の手術があり、このうち胸腔鏡下手術が30%を越えています。これは従来のごとく胸を大きく切開せず、3〜4個所の小さい穴をあけて内視鏡と手術器具を挿入し手術を行う方法で、患者さんの負担は明らかに減少し、手術後の回復も早く、適応となる患者さんには積極的に行っています。消化器一般外科グループでは年間約200例の手術を行っており、特に食道癌の患者数は県内では一番多く、九州内でもトップクラスの実績です。その手術成績も、lCU(集中治療部)の専門医による卓越した手術後の集中管理のおかげもあって極めて良好であり、全国的に高い評価を受けています。内田教授がライフワークとしてきた食道手術のこの20年間の経験をもとに、今後さらに合理的な手術、すなわち患者さんごとに手術範囲(特にリンパ節の切除範囲)を考慮したり、先に述べたような内視鏡下手術なども取り入れていきたいと考えています。また、胃の手術後の小腸を用いた代用胃を使った胃再建術においても、様々な工夫を行い、手術後の症状を軽減することに成功しており、国内外の評価を受けています。