|
医療安全管理部活動報告
〜「患者さん参加の医療安全を目指して」〜
【はじめに】
1999年の「横浜市立大学附属病院患者取り違え事故」はまだ記憶に新しいのではないでしょうか。この5年間、複雑な医療という現場の中で、患者さんの「安全と安心」を如何に保証するかが真剣に問われていると思います。この機会に、今どのような医療安全管理に対する取り組みが行われているか、またこれから何を目指していけば、患者さんにとって本当に「安全」で「安心」できる医療現場となれるのか、一緒に考えていただきたいと思っています。
【医療安全管理の取り組み ー1999年から現在ー】
厚生労働省の取り組みと本院の取り組みを一覧で示します。
医療安全に関する動向 厚生労働省の取り組み 本院の取り組み (体制整備)
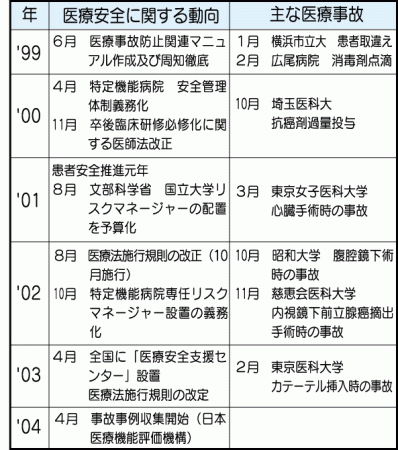 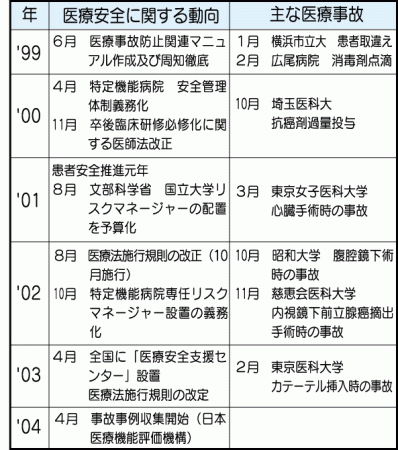
医療安全管理について、厚生労働省と全国の病院が一体となって取り組んでいます。
では、本院では実際にどんな活動が行われているのか、その一部を紹介します。

【医療安全管理活動の実際】
本院には全ての部署に「リスクマネージャー」(以下「RM」という。)と呼ばれる職員がいます。このRMが部署(病棟や外来など)で起こったインシデント(医療に関する様々なトラブルや間違い・エラーなど)に対応します。
右の写真に示すような緑のワッペンをつけている職員がRMです。多くのインシデントはこのRMが解決していますが、各部署の報告を集約し、病院全体の医療安全を考える機関が「医療安全管理部」です。医療安全管理部は院内ラウンドや職員研修など病棟や診療科の枠を越えた活動が中心になります。また、より高度の判断が必要な場合に対応するのが「病院メディカル・リスクマネジメント委員会」です。
【これからの医療安全管理】
これまでの医療安全活動は、医療者が対策を考えるといった「医療者側の視点」で行われていました。しかし、医療が人間の手で行われるがゆえに、「うっかり忘れた」、「すっかり思い込んでいた」といったヒューマンエラーをゼロにすることは、容易な事では実現できません。どんなに用心をし、予防策を採っていても、予期しない「落とし穴」に落ちることがあります。どうすればよいのでしょうか?今、重要だといわれているのが「患者さんの視点」で考える医療安全です。患者さんが「このお薬、今までのと違うよ。」と言ったことで、薬の間違いが防げたという話を聞いたり、実際に体験された方はいませんか?医療に係っているのは医療者だけではありません。患者さんも医療の一員です。一緒に「安全」を考えていただき、発言していただければと考えています。昨年の職員研修に「ささえあい医療人権センターCOML」の辻本さんに来ていただきました。そこで紹介された「医師にかかる10箇条」という小冊子を本院の売店で販売しています。これをご覧になった患者さんに是非、本院の医療安全活動を一緒に考えて頂けたら幸いです。

医療安全管理体制(大分大学医学部附属病院)
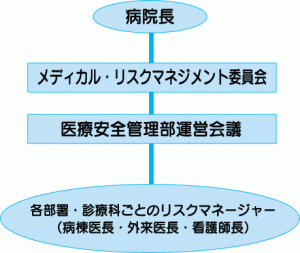
(文責 医療安全管理部 岐部千鶴)
|

