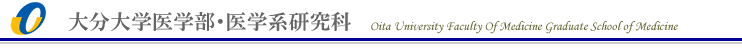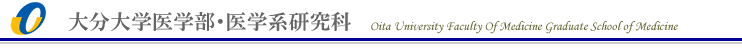項目Ⅰ 教育の実施体制
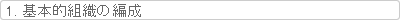
 医学科 医学科
医学科では定員は560名であるが,平成18年に在学生は570名であり, 毎年1名の科目履修生を海上保安庁から受け入れている。
これに対し, 医学部所属の教員は医学科生の教育にも参画している附属病院所属の教員を含め151名である。
また,外部の連携病院(29病院)での臨床実習のためには 大分大学臨床教授(53名),臨床准教授(1名)臨床指導医(74名)を委嘱任命している。
さらに約40名の大学院生がTAとしてチュートリアル教育の補助を行っている。
 看護学科 看護学科
看護学科の定員は260名(一般60名,3年次編入10名)で,毎年充足されている。
教員は,平成19年度末時点では教授11名,准教授3名,講師3名,学内講師2名,助教6名,助手3名の 計28名である。
各学科ともに,専任教員数を満たしている。
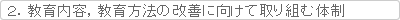
医学部教育カリキュラム改善のために医学部教務委員会の下に教養教育部会,基礎医学部会, 臨床医学部会,OSCE専門部会,CBT専門部会,看護教育部会を設置している。
 医学科 医学科
平成18年度に入学時の一般教養の生物学と医学専門教育の分子・遺伝生物学のカリキュラムを 統一し効率よい教育体系を構築した。
2年生後期よりの臓器別,機能別に統合したチュートリアル教育ではコースの再編成を行うと共に, 各担当コースに対応する医学教育モデル・コア・カリキュラムの目標対応表を作成し,教員・学生に
目標を周知徹底し,ホームページ上にも公開してその達成を目指している。
平成16年度に導入したクリニカルクラークシップを採用した58週間の診療参加型臨床実習でも 平成18年度に見直しを行い,計58週間の臨床実習とadvanced
OSCEを実施して成果を評価している。
教職員の教育能力開発については,カリキュラム作成,チューター養成,PBL事例作成法等のテーマで, 学内あるいは学外施設を利用して,年数回医学部教員教育研修ワークショップを開催したり,医学教育財団
などが主催するワークショップなどに多くの教職員を派遣してきた。
 資料5-2-1
:FD開催状況 資料5-2-1
:FD開催状況  PDFファイル PDFファイル  Excelファイル Excelファイル
医学教育モデル・コア・カリキュラムで要求されている漢方医学の教育者を養成するための講座を 開催するとともに「漢方外来」も設置した。
以上のような取り組みの結果,医師国家資格試験合格率は全国平均以上を維持している。
 看護学科 看護学科
年度毎に教員による授業評価と卒業生対象のカリキュラム評価調査の結果を冊子Course Evaluationにまとめ,教育改善の資料としている。
 資料5-2-2
: Course Evaluation(抜粋) 資料5-2-2
: Course Evaluation(抜粋)  PDFファイル
PDFファイル  Wordファイル
Wordファイル
平成16年度以降は,教育評価の指針に基づき組織的に行っている。
 資料5-2-3
: 教育評価の指針 資料5-2-3
: 教育評価の指針  PDFファイル PDFファイル  Wordファイル
Wordファイル
また,教育活動を組織的・効率的にすすめるために,看護学科会議(学科の最高議決機関)の下部組織にカリキュラム部会,看護学実習部会を設け,教育上の問題・課題の解決策を検討している。これら部会の構成員には,それぞれ医学部教務委員会,医学部看護ユニフィケーション・システム推進委員会の委員が加わり,医学部組織全体との連携を図っている。
平成17年度よりカリキュラム改正に向けての準備作業をすすめているが,平成19年度にはカリキュラム検討ワーキングを立ち上げ,平成21年度適用に向け検討を重ねている。
FDに関しては,この教育評価の他,平成18年度以降はFDの指針を作成し,FD部会を中心とした組織的なFD活動をすすめている。
 資料5-2-4
: FDの指針 資料5-2-4
: FDの指針  PDFファイル PDFファイル  Wordファイル
Wordファイル
学生の看護実践能力の育成に向けて,平成18年度に附属病院看護部との協働で「医学部実習指導検討会」を 組織し,実習指導の具体的課題の検討や研修会開催等を行っている。本会を通じて,実習指導者(看護職員)による
実習指導体制づくりが促進され,学生からも“丁寧でわかりやすい助言により,ケアの意味,新たな視点・具体的な 介入を考えることができた。一緒に考えようという姿勢や励ましが心強かった(平成19年度看護過程実習授業評価)
”という声がきかれた。
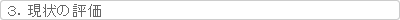
平成13年の外部評価委員からの指摘を受け,教務委員会の下に5つの専門部会を設け責任者を設定した。また,医学部附属医学教育センターを設置して専任教授を置き,カリキュラム内容の重複や欠落を発見して改善したり,卒前・卒後教育全体を見直す作業を行うと共に,教育改善と教員の教育力向上に向けたFDを組織的・計画的にすすめている。
|
|