|
もくじ |
| 第2号 H 12.7/1 |
| 医薬分業について |
| 内科第二紹介 |
| 外科第二紹介 |
| 7階西病棟紹介 |
| 検査部紹介 |
| ET・WOCナース紹介 |
| かけはしホーム |
| おくすりのコーナー
このコーナーでは、読者のみなさんがくすりと上手につき合っていく上で、少しでも役立つ話題を提供していきたいと思います。 錠剤や粉薬などの内服薬は、口からからだの中に入ると、まず、食道を通り、胃へと進んでゆきます。このとき、くすりと一緒に飲む水の量が少なかったり、服用後、すぐに横になると、くすりが食道にくっついてしまい、そこで潰瘍を引き起こす原因となります。コップ一杯の水や白湯などと一緒に服用し、飲んでもしばらく体を起こしておかないといけないのはこのためです。 食道を通り抜けた錠剤は、胃にたどり着き、胃の運動などで壊されて粉状となり、腸へと進みます。くすりの中の有効成分は、主にここで溶け出し、腸管壁から吸収され血液中に入ります。
さて、腸管壁より吸収されたくすりは、門脈という血管を通って肝臓に入ります。肝臓には、たくさんの酵素があり、くすりのように体にとって異物となるものを無害なかたちに変える働き(代謝)を持っています。この肝臓での代謝を逃れたくすりは、血液の流れに乗って全身に運ばれ、必要とされる場所にたどり着き、ここで初めて、くすりとしての仕事(薬効)がなされます。 一度仕事を終えたくすりは、血液に乗って再び肝臓へと戻り代謝を受けます。このとき、代謝されなかったくすりは、再び全身を巡る旅に出かけます。くすりは、いつまでもからだの中にとどまっていると、からだにとって良くないことを引き起こす場合が多いので、できるだけ速やかに体の外に出ていくことが望まれます。 肝臓でかたちを変えたくすりは、腎臓を通って尿中に、もしくは、肝臓でつくられる胆汁に乗って糞便中に出て行きます。また、くすりによっては、かたちをかえないまま、からだの外に出て行くくすりもあります。 このようにして、口から入ったくすりは、体中を駆けめぐり、最後には、かたちを変え、もしくはそのままのかたちでからだの外に出て行きます。 くすりは、正しく使えば患者さんにとって非常に頼もしい存在となりますが、誤って使用すると、いろいろと問題を引き起こすことがあります。もし、くすりのことでわからないことや聞きたいことなどございましたら、医師や薬剤師に気軽にお尋ね下さい。 (文責 薬剤部医薬品情報管理室 林 哲治)
|

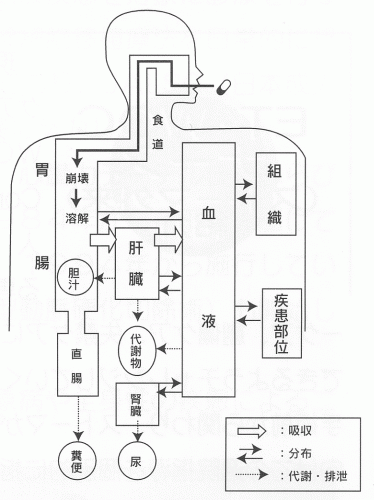 ところで、くすりの飲み方には、「食前」、「食後」などがありますが、なぜ、このように飲み分けないといけないのでしょうか。それは、くすりの吸収と深い関係があります。例えば、あるくすりは、空腹時に服用すると、一気に吸収され、急激に血液中のくすりの量が増えてしまい、通常よりも強い効果が現れます。また、逆に、食事をとらなければほとんど吸収されず、効果を示さないばかりか、消化性潰瘍を引き起こしてしまうくすりもあります。ある糖尿病薬は、食事の直前に服用しなければ、効果が現れず、結果として、血糖値が上昇し、高血糖を引き起こしてしまうことがあります。くすりをいつ服用するかは、時として、くすりの効果を大きく左右しますので十分注意を払う必要があります。薬袋の表に書かれた服用方法を必ず確認するようにして下さい。
ところで、くすりの飲み方には、「食前」、「食後」などがありますが、なぜ、このように飲み分けないといけないのでしょうか。それは、くすりの吸収と深い関係があります。例えば、あるくすりは、空腹時に服用すると、一気に吸収され、急激に血液中のくすりの量が増えてしまい、通常よりも強い効果が現れます。また、逆に、食事をとらなければほとんど吸収されず、効果を示さないばかりか、消化性潰瘍を引き起こしてしまうくすりもあります。ある糖尿病薬は、食事の直前に服用しなければ、効果が現れず、結果として、血糖値が上昇し、高血糖を引き起こしてしまうことがあります。くすりをいつ服用するかは、時として、くすりの効果を大きく左右しますので十分注意を払う必要があります。薬袋の表に書かれた服用方法を必ず確認するようにして下さい。