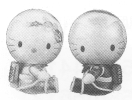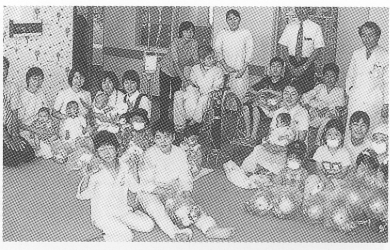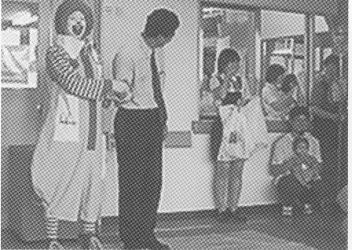|
もくじ |
| 第3号 H 12.10/1 |
| 総合診療部について |
| 内科第3紹介 |
| 7階東病棟紹介 |
| 放射線部紹介 |
| Q&Aコーナー |
| ふれあいコンサート |
| かけはしホーム |
| 市 民 公 開 講 座
「日本人と臓器移植」─あなたはドナーになれるか?─ 大分医科大学外科学講座(第二) 内田 雄三 いのちある ひとあつまりて我が母の いのち死行くを 見たり死ゆくを これは大正2年、母親の臨終に立ち会った斎藤茂吉が詠んだ歌である。今まさに屍体と化しつつある老いた母親、さまざまな思いをこめてそれを見つめる肉親・縁者の視線、もはや何人も止めることの出来ない死への流れ、人間の力をはるかに超えた自然の大きな力に全てをゆだねて祈るしかない‥・。この情景こそがわれわれふつうの人間が体験する死の認識の過程である。医師による死の判定の告知は、このゆっくりと流れる過程の中の一瞬でしかありえない。すなわち、死の認識とは死にゆく人のまわりに集う縁者の思い思いのメンタリティの流れそのものであり、決して一瞬の容認を意味しない。 何かの本で読んだ話であるが、アンデスのある地方から出土した8才の男児のミイラは、生前その子が小児麻痺であったことを裏付けるかのように下半身が異常に未発達であった。そしてその子のミイラのそばには動物の強そうな足の骨が1本副葬されていた。この子の親は、愛しいわが子がこの世での不幸な8年間の人生を閉じたとき、次の世では強い足を持って生まれてくるようにと願って動物の足を副葬したのであろう。 子がみる親の死、親がみるわが子の死、それは死が単なる生理現象の停止にとどまらないことを意味し、科学的手段に基づく生理現象の停止の認識は死の認識そのものではないことを物語っている。 20世紀になって医学は飛躍的な発展をとげ、欧米においては臓器移植が日常的な治療の手段の一つとして行われるようになった。本邦においては、肉親からの生体臓器移植は普及したが、1固体が死ぬことを前提とする脳機能停止体からの臓器移植は欧米におけるほど受容されていない。これは文明の進歩の量的な違いによるものではなく、「死の認識」「屍体への思いいれ」さらには「次の世への期待」などの質的な違いに基づくものではないだろうか。生体臓器移植のドナーを希望する肉親の思いには、先ほどのミイラの話に共通する肉親の哀しいほどの深い思いがありはしないか? 古代から日本人の心の奥深くに潜在する、”次の世への期待となぐさめ”にも似たある種の感情について、私達はもっと思いを馳せる必要があるように思われてならない。欧米で行われたものとは少し異なった、日本人の死生感を肯定した形での移植への理解を求める方法を、今こそ外科医の側から提案する必要があるのではないだろうか。 今回の市民公開講座はまさにその試みの最初の一つである。
| ||||||||||||||||||