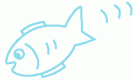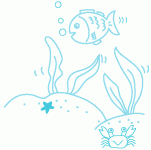|
もくじ |
| 第10号 H 14.7/1 |
| 地域医療連携室開設 |
| 病院のHP |
| 3階西病棟紹介 |
| Q&Aコーナー |
| 看護の日 |
| 七夕会 |
| 患者さんの声 |
| お知らせ |
| かけはしホーム |
第10号 H 14.7/1
≪栄養相談室から≫

|
このコーナーでは、読者のみなさんが、少しでも食事に関心をもっていただくために役立つ情報を提供していきたいと考えています。第二回目の今回は、近頃よく聞く“あの歌”をテーマにお話しします。 ♪さかな さかな さかな〜 さかな〜を〜食べ〜ると〜♪ このフレーズ、みなさんもどこかで耳にされたことがあるのではないでしょうか。最近なにかと話題になっているこの曲は、「魚は体に良い」とうたっていますが、魚には一体どんな効果があるのでしょう? 魚をよく食べる地域の人々は、そうでない地域に比べて、心筋梗塞や脳梗塞、がんなどの発症率が少なく長寿であるといった数多くの報告があります。そのことから注目を集めたのがDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)という、魚油に含まれる脂肪酸(多価不飽和脂肪酸)の一種で、背が青く脂肪の多い魚(いわゆる青魚)に比較的多く含まれている物質です。 DHAやEPAには、血管壁をやわらかくしたり血小板がかたまるのを防いだりすることにより、血液の粘りを減らして流れをよくし、動脈硬化を予防する作用があることが明らかになっています。また、コレステロールや中性脂肪を下げたり、アレルギーを起しにくくする働きもあるといわれています。この他にもDHAは脳の活性化や老化防止にも効果がみられています。つまり、魚は生活習慣病の予防に適した食品ということができます。 とはいえ、体に良いものでも食べ過ぎはよくありません。では、どのくらいの量を食事にとりいれていくのが良いのでしょうか?
魚と野菜、穀物を中心とした伝統的な日本食は、蛋白質・脂質・炭水化物の摂取比率が理想値に近いといわれています。食生活を見なおして、病気に対する抵抗力を培い、健康長寿をめざしましょう。♪さかなは僕らを、まっている!♪
(文責 栄養管理室 廣田 優子) |