|
もくじ |
| 第9号 H 14.4/1 |
| これからの医療と… |
| 治療最前線・泌尿器科 |
| お知らせ |
| 5階東病棟紹介 |
| Q&Aコーナー |
| 総合診療部 |
| 医療安全管理部 |
| 患者さんの声 |
| かけはしホーム |
≪お酒とくすり≫
|
お酒の主成分であるアルコールは体の中に入ると胃や腸から吸収された後、肝臓に運ばれ、そこで分解酵素によりアセトアルデヒドや酢酸という物質に変えられます。このアセトアルデヒドや酢酸は血液に乗って全身に運ばれ、筋肉や脂肪組織でさらに分解され炭酸ガスと水となり体の外に出てゆきます。しかし、お酒を飲み過ぎたり肝臓が疲れていたりすると、このアセトアルデヒドが体内にたまり、顔面紅潮、動悸、吐き気、寒気、頭痛、血圧降下などの、いわゆる二日酔い症状を引き起こします。 一方、肝臓で分解されなかったアルコールは血液に乗って脳に達し、麻酔薬と似た作用を示します。麻酔の作用はその深さにより4つの段階に分かれますが、麻酔薬はより深い時期が長いのに対してアルコールは浅い時期が非常に長く、精神的な抑制が解かれることによって開放的な気分になります。これがアルコールによる酔いの正体です。 ところで、お酒がくすりに対して与える影響にはどのようなものがあるのでしょうか? まず一つ目として、お酒の主成分であるアルコールによる影響があげられます。アルコールには、血管を広げ血圧を下げる作用や脳の働きを抑える作用がありますので、高血圧のくすりや精神安定剤、睡眠薬などの効果を強めることがあります。また、頭が痛いからといって鎮痛剤を服用すると、アルコールにより荒れた胃腸をさらに悪化させる場合もありますのでご注意ください。二つ目としては、肝臓の分解酵素が関係する場合があります。例えば、セフェム系と呼ばれる抗生物質の一部は、アセトアルデヒドの分解酵素を阻害してひどい二日酔い症状を引き起こします。また、くすりを分解するチトクロームP450と呼ばれる酵素は、同時にアルコールも分解しますので、くすりとアルコールが同時にあるとくすりを充分分解しきれずに、結果としてくすりが体の中に長くとどまり効果が強くなることがあります。くすりの服用後2時間はお酒を控え、お酒の量も少なめにすると良いかと思います。 (文責 菅田 哲治)
|

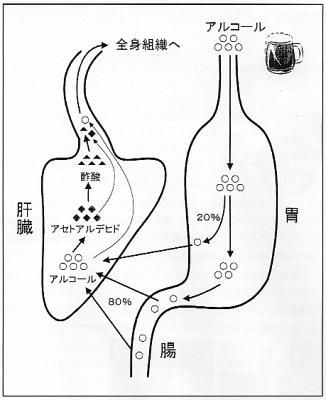 春を迎え花見や歓迎会などお酒を飲む機会が増えていませんか?今回はお酒とくすりについてお話しします。
春を迎え花見や歓迎会などお酒を飲む機会が増えていませんか?今回はお酒とくすりについてお話しします。