
輸血部
輸血部は血液製剤の検査、管理、輸血副作用の監視、および使用記録の保管管理を行う部門です。輸血療法が必要な患者さんに対して検査を実施し、安全かつ適正な血液製剤を供給することを目的に業務を遂行しています。輸血療法委員会を開催し、病院全体で輸血療法が安全に行われるよう仕組み作りや改善に取り組んでいます。
輸血責任医師の下、検査体制を整え、血液製剤の管理、輸血後副反応の監視や輸血製剤の使用記録の保管管理を行っています。また、造血幹細胞移植やCAR-T細胞療法などの細胞療法にも携わり、多職種連携のチーム医療の一員として、患者さんの治療のサポートをしています。
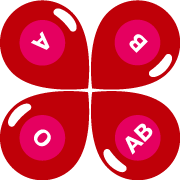
輸血は病気や薬の影響などで十分に血液をつくることができない場合や、事故や手術などで大量出血した場合に行います。輸血により、不足した成分を補充し、症状の改善を図ります。
血液は、赤血球や血小板、白血球などの細胞成分と、液状成分で構成されています。赤血球を補充することを目的に製造された製剤が「赤血球液」、血小板を目的に製造された製剤が「濃厚血小板」、細胞成分以外の液状成分を目的に製造されたのが「新鮮凍結血漿」です。いずれも献血によって提供された血液から作られます。
赤血球を補充することで、全身に十分な酸素を供給する目的で使用されます。
血小板を補充することで補充することで、出血を防ぎ、止血を促進する目的で使用されます。
血漿には各種の凝固因子が含まれ、血小板と協働して止血する役割があります。凝固因子を含む血漿を補充し、止血を助けるために使用されます。
また患者さん自身の血液をあらかじめ採取して保管し、手術に使用する「自己血」もあります。手術などで血液を使用する日にちと量がわかっている患者さんを対象とします。適応の条件があり、誰でも使える方法ではありません。
適合しない血液が輸血されること、さまざまな副反応が起こります。それを防ぐために、ABO血液型とRh血液型の検査を行います。
ヒトの赤血球には、ABO血液型やRh血液型以外にもたくさんの種類の血液型があり、全く同じ血液型の血液を輸血することはほとんど不可能です。妊娠や輸血などにより、自分とは異なる血液が身体の中に入ると、その血液に反応する抗体がつくられることがあり、これを不規則抗体と呼びます。
患者さんの血液中に不規則抗体があると、輸血で副反応が起こることがあるため、不規則抗体の有無を事前に検査します。
輸血用の血液製剤を患者さんへ投与したとき、患者さんの体内で何か反応が起こらないかどうかを、あらかじめ試験管内で検査します。体内とは異なる環境ではありますが、輸血の安全性を確保するために重要な検査です。
本来、自分の赤血球には反応しない抗体が、病気や薬の影響により、体内で反応する場合があります。また、新生児では母親から移行した抗体により、貧血がみられることがあります。そのような場合に実施する検査です。
ABO血液型検査で、通常検査のみでは血液型を判定できない場合があります。
そのような時に精査を行い、A、B、O、AB型の何に分類されるのか判別し、安全に使用できる血液型を判定するための検査です。
白血球細胞表面にある抗原、CD3抗原陽性細胞およびCD19抗原陽性細胞の比率を測定することによりリンパ球のうち、T細胞とB細胞の比率と個数を評価します。
白血球細胞表面にある抗原、CD4抗原陽性細胞およびCD8抗原陽性細胞の比率の測定と、個数の測定し、T細胞のサブセットを評価します。
造血幹細胞移植のために採取された末梢血幹細胞について、造血幹細胞の指標であるCD34抗原陽性細胞の個数を測定します。患者さんへ投与する細胞数はある程度決まった個数が必要なため、末梢血幹細胞移植には欠かせない検査です。
造血幹細胞移植に必要な末梢血幹細胞の凍結保存を行います。保存に適した状態に調製し、使用時まで凍結保存します。
移植後のGVHDに対する治療法である間葉系幹細胞製剤の調整、管理を行います。
ドナーリンパ球の処理、凍結保存、管理を行います。
患者さん自身のリンパ球を採取後、遺伝子導入を行い、腫瘍細胞を攻撃するように改変して体内に戻す治療法です。輸血部では、患者さんのリンパ球が採取された後、適切に調製・凍結保管を行います。
大量出血などで失われたフィブリノゲンの補充目的に使われるクリオプレシピテートの作成を行います。
各種輸血用製剤は24時間温度管理された保冷庫で保管、管理されます。

